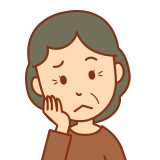
大事にしていた器、欠けちゃった~(( ノД`)
日常のショッキングな瞬間、誰もがタイムマシンで1分前に戻りたいと切実に思う瞬間ですね。
これから60代や70代でも継続できる趣味はないかと探していたら…金継ぎという漆で器を修理する趣味にはまるまでのお話です。
金継ぎは、金を蒔くまでがとてつもなく長く忍耐のいる作業と知る

こちら、訪れたワークショップにて、先生にかなり作業を手伝ってほぼ先生が対応された一品になります。
こちらのワークショップでは初心者コースとして欠けには麦漆ではなくてシリコンのような、すぐに固まるものをつけ、紙やすりで段差をなくしたその上から漆→金を蒔きました。
簡素化された手順とはいえとても時間がかかりました。
まず、欠けに盛ったそのセメントみたいなのがすぐに固まるのですが固くなりすぎて、カッターで境目がないように余分なところを削り、サンドペーパーの番手を替えながら表面を滑らかにしていきます。
何度先生にみてもらっても指で表面をさわって「もうちょっと!!段差があるから」。
もう、、指紋がなくなるかと思うくらいペーパーをかけます。
こういうところのこだわり・丁寧さが美しい金継のコツなんですね。その時間の長さを想うと、うるしをつけて金粉を蒔く一瞬ときたら一瞬。ふわりと光る金粉に、今までの苦労が報われます。
これに味を占めて、本格的に自宅で漆を使ってあれこれしてみようと思い立ちます。
金継セットを買う。 漆の扱いに慣れよう

こちら、「金継コフレ」をネットで入手。京都の堤淺吉漆店さんのもの。
いきなりは怖いので「コフレの前に「拭きうるしセット」なるものを買って、セットについていたお箸ではなく、吉野杉のお弁当箱に漆をほどこしてみようとおもいまして。

はい、こちら 2018年に奈良 興福寺の中金堂 落慶記念のお弁当に使われていた、吉野杉のお弁当箱です。記念にとっていてお弁当箱として活用していたのですが水が沁みてきたので、「ふきうるし」にて撥水+耐久性をあげることができればと企みます。

漆を塗って乾かすこと × 5回。 いい艶になってきました。 一度塗ると1週間乾かすので5回だと5週間。待っている時間もいとおしく、晴れてマイ漆お弁当箱ライフの始まりです。
漆は英語で japan と書きますね。 ざ・日本の文化に触れております私。
案の定 漆にかぶれる
漆はかぶれると申しますが、終わってからすぐにはかゆみはでません。
全然大丈夫、私耐性あったのねと奢っていた次の日、あれ?という感じでじわじわとかゆみが襲ってきます。
発疹や赤くただれたみたいになりますが、べったりつかなければそこまでひどくはなりませんし、1週間程度で治まって跡も残らなかったです。
しかしかゆいものはかゆい。こうやって書いているだけでもかゆみを思い出す…。
漆が直接肌につかないように、手袋+長袖など工夫が必要で、もし付着してしまっても、水ではなくサラダ油などで落とします。
水やせっけんで洗うとかゆみの範囲が広がってしまうので要注意。
昔の人は漆を発見しただけでもすごいのにこんな対処法とかよくみつけられたなとこれまでの長い歴史に敬意。
大切な器の出番が増えました
これで漆の扱いも少し慣れて、本格的に漆を使って欠けを修理していきます。
塗って乾かすの繰り返し。 漆を薄めたり落としたりする「テレピン油」(セットに入っています)のにおいがきついので、主に自宅で一人でいる日にひっそり作業をします。
①欠けを埋める場所に漆を塗る→②欠けを埋める(麦漆)→③乾いたら削る・ペーパーをかける→④絵漆を塗って金粉を蒔く
至福の金継ぎ時間
ものをなおして長く使う。気に入った器を修理する。この時間、至福です。
まだ割れたものをくっつけたことはないのですが少しずつ慣れつつ。
しまいこんでいる食器ももしもの時には修復できるという気持ち。
お気に入りの器を出して、食事の時間をより楽しんで。

↓練習あるのみ


コメント